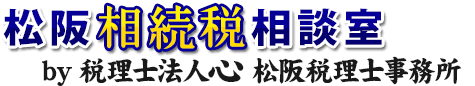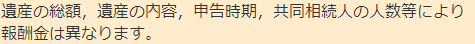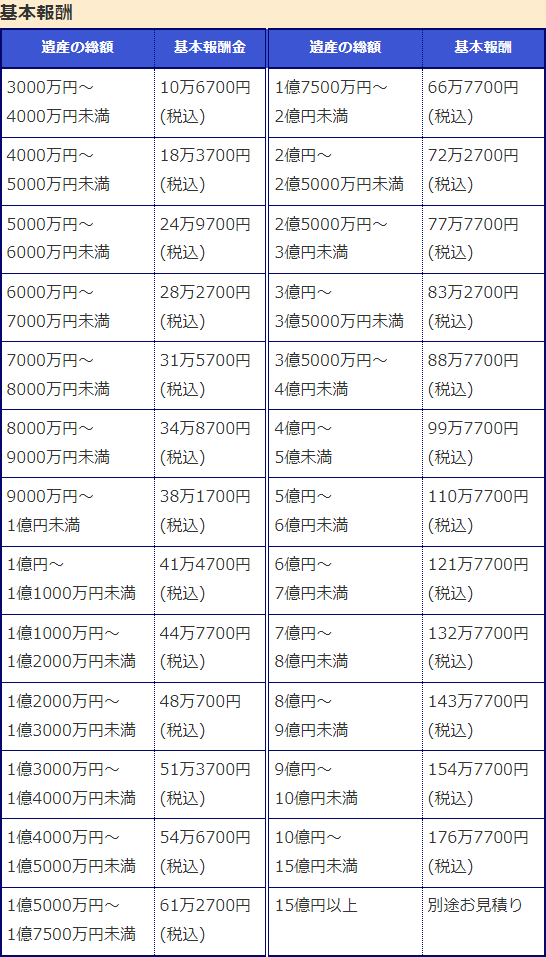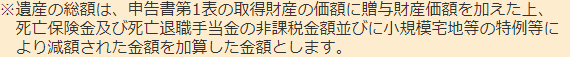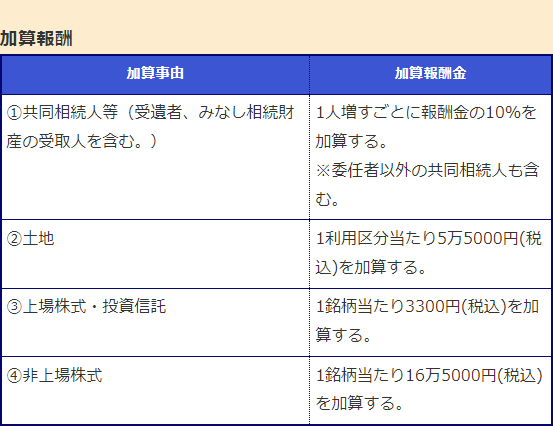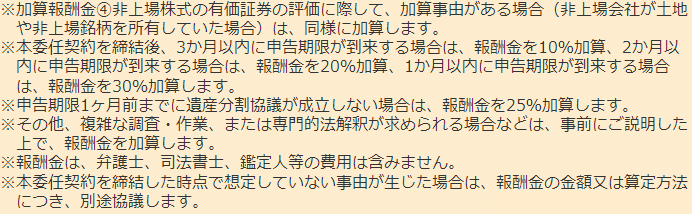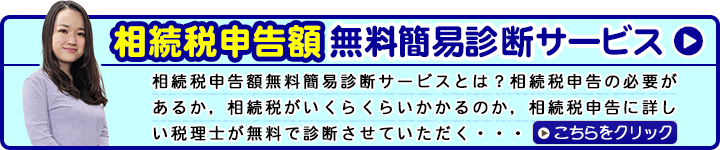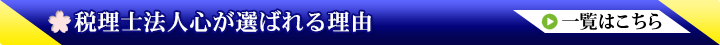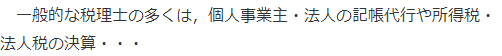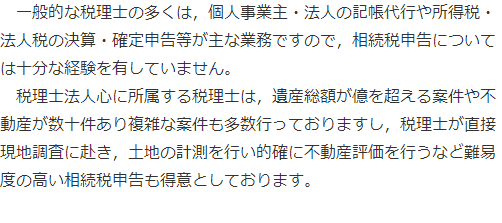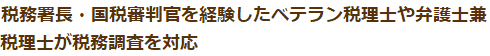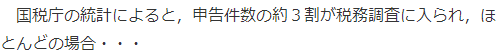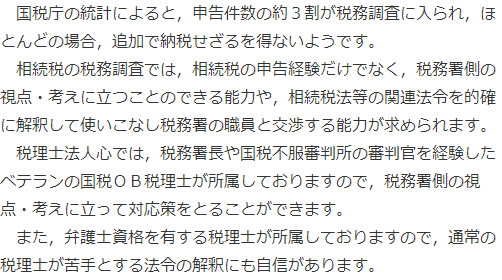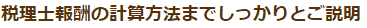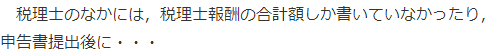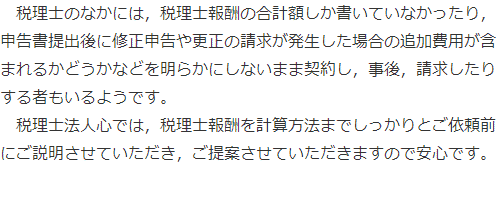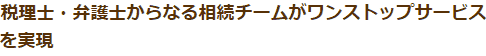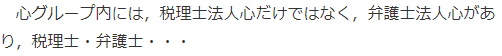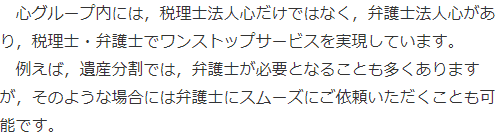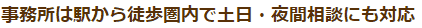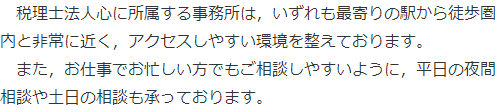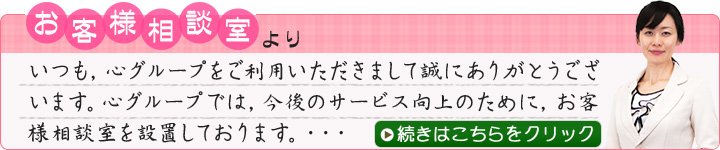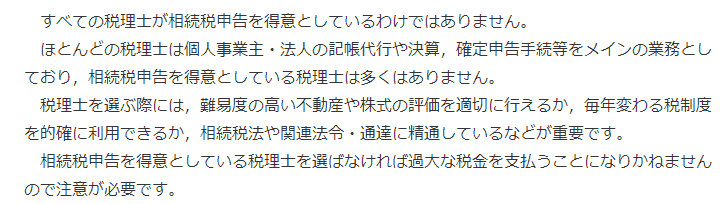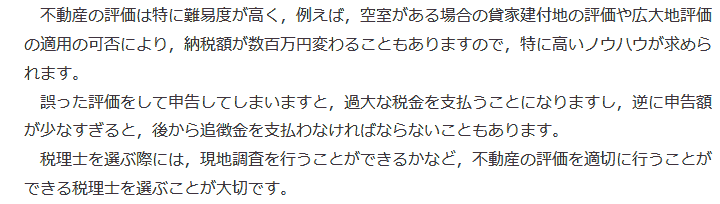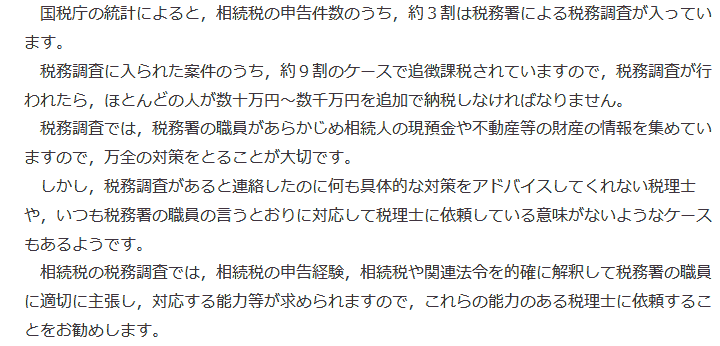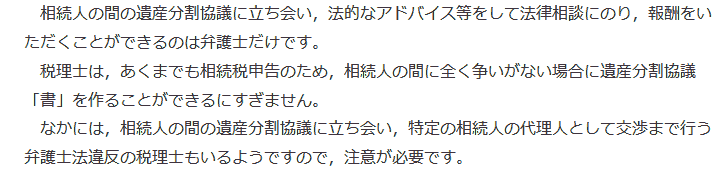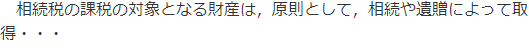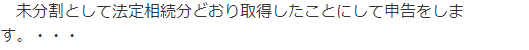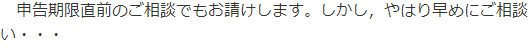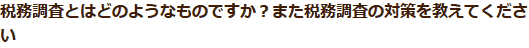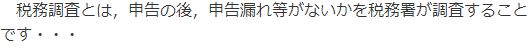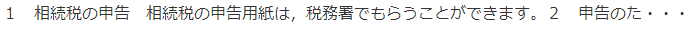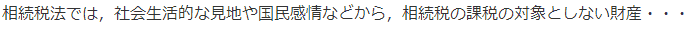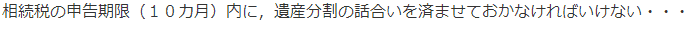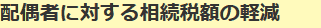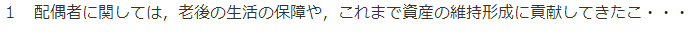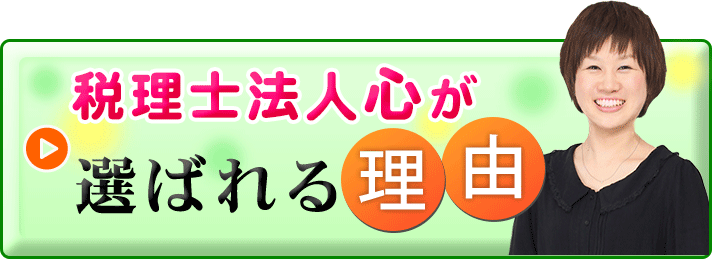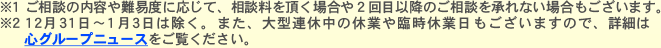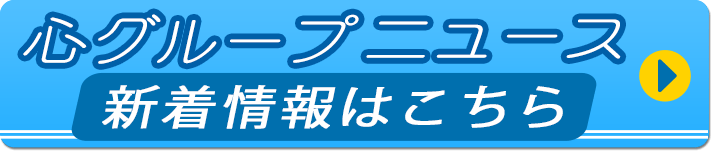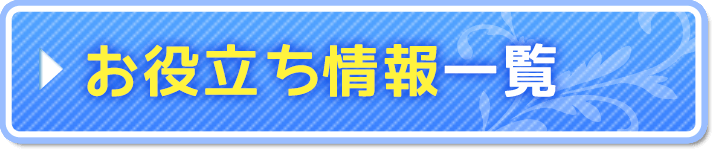相続税の生前対策をお考えの方へ
1 相続税の生前対策を行う場合の注意点

最近では、書籍やインターネット等で、容易に相続税対策についての情報を得ることができるようになってきています。
また、銀行員や保険会社の人と話をすると、様々な相続税対策が紹介されることがあります。
しかし、実際に相続税を行うにあたっては、このような知識を適切に用いる必要があります。
ここでは、このような知識を適切に用いることができなかったため、相続税対策が意味をなさなくなってしまった例を説明し、適切な知識に基づく相続税対策の必要性を明確にしたいと思います。
2 相続税対策のために生命保険の契約を行った例
この例では、被相続人が、生前、生命保険が相続税対策になるという話を聞いており、生命保険の契約が組まれていました。
このため、死亡保険金については、相続税の申告対象から除外して申告を行いましたが、後日、税務署から、死亡保険金についても相続税の対象になるという指摘がされました。
このため、相続人の方が、死亡保険金は相続税の課税対象にならないのではないか、税務署の言っていることは間違いではないかと思い、当法人に相談に来られました。
確かに、死亡保険金については、500万円×法定相続人数までは、相続税の非課税枠が設けられています。
ただ、このような非課税枠が設定されるのは、相続人が受け取った死亡保険金に限られます。
裏返せば、死亡保険金を受け取ったのが相続人でなければ、その死亡保険金については非課税枠を用いることができないということになります。
今回の事例では、生命保険契約が組まれ、死亡保険金の支払がなされていましたが、死亡保険金の受取人になっていたのは、被相続人の孫(その親は存命)でした。
この場合、死亡保険金を受け取ったのは相続人ではありませんので、その死亡保険金について非課税枠を用いることができませんでした。
このように、生前対策の代表例といわれる生命保険でさえ、適切な知識に基づいて対策を行わなければ、有効にならないことが分かります。
生前対策においては、適切な知識に基づいて行うことが必須であるといえます。
相続税で困った場合の相談先
1 相続税の相談を受けることができる専門家は税理士のみ

相続に関係する専門家は様々ですが、相続税の相談先となり得るのは、税理士だけです。
税金に関する業務については、税理士が無償独占しているといわれます。
税金に関する業務には、納税者の代理人となって申告すること、申告書を作成すること、税金に関する相談を受けることが、すべて含まれています。
また、無償独占とは、仮に無償で業務を行う場合であっても、税理士以外の専門家が税金に関する業務を行うことはできないということです。
このため、司法書士、行政書士等はもちろん、いわゆるコンサルタントであっても、税金に関する業務を行うことはできないとされています。
以上から、相続税の申告をしなければならない場合は、税理士に相談しなければならないこととなります。
2 相続税に詳しい税理士に相談すべき
とはいうものの、普段から依頼している税理士がいない場合は、どの税理士に相続税の相談をすべきか、迷うところです。
また、普段から依頼している税理士が相続税に詳しくないため、別の税理士に相談する必要が生じることもあり得ます。
このような場合、相談先の税理士をどのように見つければよいのでしょうか。
1つの重要な判断基準は、その税理士が、相続税に詳しいかどうかということです。
前提として、税理士であれば、すべての税目を普段から取り扱っているというわけではありません。
さらにいえば、多くの税理士は、所得税、消費税、法人税を取り扱うことが多く、相続税を集中的に取り扱っている税理士は少数です。
これは、一般的な税理士が相続税を取り扱うのが、顧問先で相続が発生した場合等に限られているためです。
相続税は、税額が大きくなりがちであり、かつ、少しの考慮要素の違いにより、納付すべき税額が大きく異なってくることがという性質を持っています。
このため、相続税においては、特に、適切な申告を行い、納税者に不利益が生じないようにする必要性が大きいです。
以上の理由から、相続税に特化した税理士にご相談いただくことをおすすめします。
相続税について税理士に相談するタイミング
1 税理士に相談するべきタイミングについて

相続税に関する相談は、どのようなタイミングで行えばよいのでしょうか。
結論から述べると、相談は早ければ早いほど良いです。
相続税については、被相続人が亡くなったことを知ってから10か月以内に、税務署に申告書を作成した上で、納付をしなければならないこととなっています。
10か月以内に申告書の提出と納付を行うことができなければ、相続税の本税だけでなく、加算税や延滞税を納付しなければならなくなる可能性があります。
また、加算税や延滞税の問題だけでなく、期限に間に合わないことにより、相続税に関する特例を用いることができず、多額の税金を納付しなければならないという事態が生じることもあり得ます。
この点について、以下で詳しく述べたいと思います。
2 小規模宅地等の特例の利用
相続税の申告を行う際には、すべての財産について評価を行い、相続税の計算を行うこととなります。
この評価額が低ければ低いほど、課税される相続税は少なくなります。
宅地についても、評価額を算定した上で、申告書を作成することとなります。
要件を満たす宅地を一定の親族が取得した場合には、小規模宅地等の特例を用いることにより、限度面積まで、評価額を20%から50%まで減額することができます。
具体的には、被相続人等が住居として使用していた土地については、配偶者や同居親族が取得した場合には、限度面積まで、評価額を20%まで減額できます。
被相続人等が事業のために使用していた土地については、事業を引き継いだ親族が取得した場合には、限度面積まで、評価額を20%まで減額できます。
被相続人等が賃貸のために使用していた土地については、限度面積まで、評価額を50%まで減額できます。
このように、小規模宅地等の特例を用いることにより、宅地の評価額を大きく減額することができる可能性があります。
このような小規模宅地等の特例を用いるには、特例の適用対象になる宅地について、その取得者が確定している必要があります。
言い換えれば、特例の適用対象になる土地について、遺産分割協議が成立している必要があるのです。
遺産分割協議が成立したことについては、遺産分割協議書に相続人全員の実印を押印し、相続人全員の印鑑証明書を添付することにより、証明することとなります。
これらの書類を相続税の申告書に添付しなければ、当初申告の段階から、小規模宅地等の特例を用いることはできません。
つまり、小規模宅地等の特例を適用するためには、特例の適用対象となる土地を誰が取得するかについて相続人全員で合意し、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印を得るとともに、相続人全員の印鑑証明書を取得する必要があります。
裏返せば、相続人の1人でも、誰が特例の適用対象になる土地を取得するかについて同意しない場合には、小規模宅地等の特例を適用することはできないこととなります。
このような意見調整と書類の作成、取得には、かなりの時間を要することもあります。
このため、小規模宅地等の特例の適用を検討する場合には、時間的な余裕をもって申告の準備を行うのが望ましいです。
このように、特例の適用を受けるための準備を行うという観点からも、早期に税理士へ相談しておくとよいかと思います。
不動産評価に強い税理士に依頼すべき理由
1 なぜ不動産評価に強い税理士に依頼するべきなのか

不動産の評価は、税理士によって結果が大きく異なります。
不動産の評価額は大きい金額になることが多いですので、個々の税理士が算定する相続税の額も大きく異なってくることとなります。
妥当な評価額に基づいて相続税を納付するためにも、不動産評価に強い税理士に依頼することが重要であるといえます。
ここでは、税理士によって不動産評価が大きく異なった例を紹介し、相続税申告での不動産評価の重要性を説明したいと思います。
2 不動産評価が税理士によって大きく異なった例
この例では、路線価地域の宅地の評価を行う必要がありました。
路線価地域の宅地については、国税庁のホームページ等で路線価図を確認し、宅地に接している道路の路線価に地積を乗じ、宅地の評価額を算定します。
参考リンク:路線価・国税庁
この例でも、当初、税理士は、宅地に接している道路の路線価に地積を乗じることにより、不動産の評価を行っていました。
ところが、地図を確認する限りでは、宅地に接している道路が河川に沿って走っていました。
現地も確認したところ、その道路が、河川の堤防部分に存在していました。
そこで、市町村役場で確認したところ、その道路が河川管理道路であることが判明しました。
宅地に河川管理道路が繋がっていたとしても、接道義務を満たしていることとはならず、その宅地に建物を建築することはできないこととなります。
したがって、その宅地は、無道路地として扱うべきであることが確認できました。
無道路地については、建物の建築が困難ですので、評価額が下落します。
結果、相続税の額も減額されることとなりました。
このように、不動産評価に強い税理士にご依頼いただければ、納める相続税の金額を適切なものにできる可能性が高まります。
相続税について相談する税理士を選ばれる際は、この点も考慮してご検討いただくとよいかと思います。
相続税を依頼する場合の税理士の選び方
1 相続税の申告

相続税の申告は、詳しい知識がない中で行うと負担も大きいかと思いますので、税理士に依頼して任せようとお考えの方も多いのではないでしょうか。
相続税を依頼する税理士の選ぶ際には、以下の点に着目するのが良いでしょう。
2 最新の規定をキャッチアップしていること
相続税については、大小問わず、ほぼ毎年、何らかの規定の変更が行われています。
このような規定の変更は、相続税の申告にあたっての落とし穴になりがちです。
注意しなければならないのは、過去の規定では税額軽減を用いることができたのに、最新の規定ではそれができなくなった場合です。
このような場合に、過去の規定にしたがって相続税の申告をしてしまうと、誤って税額軽減を用いることとなってしまい、後日、加算税や延滞税が課税されるおそれがあります。
逆に、過去の規定では税額軽減を用いることができなかったのに、最新の規定ではできるように変更された場合も、注意したいところです。
このような場合に、過去の規定にしたがって税額軽減を用いることなく申告してしまうと、本来納付すべき税額よりも多額の相続税を納付することとなってしまいかねません。
例えば、かつては、二世帯住宅については、家の中で自由に行き来ができる場合に限り、被相続人と同居している世帯と扱われ、同居親族についての小規模宅地等の特例を用いることができるとされていました。
ところが、平成27年の税制改正により、区分所有登記がなされている場合には、被相続人と同居している世帯とは扱われない一方、区分所有登記をしていない場合には、被相続人と同居している世帯と扱われ、同居親族についての小規模宅地等の特例を用いることができるようになりました。
こうした最新の規定をキャッチアップしていなければ、正確な相続税の申告を行うことはできません。
最新の規定をキャッチアップするためには、普段から規定の変更についての情報を把握し、必要な場面で適用する体制を作っておくことが必要不可欠です。
3 民法の規定や判例を把握していること
相続税は、他の細目と比較して、法律の世界との関連性が深い分野です。
税理士は法律の専門ではありませんが、相続税の申告を行うに当たっては、ある程度、民法の規定や判例を知っておく必要があります。
例えば、土地の評価を行うにあたり、その土地に借地権が設定されているかどうかによって、大きく評価額が異なってくることがあります。
借地権が設定されている場合は、その土地の評価額から、借地権割合を差し引くことができ、大きく評価額を減少させることができるからです。
それでは、次のような場合に、借地権が設定されていると言うことはできるのでしょうか?
被相続人が所有する土地を第三者に賃貸していました。
賃借人は、土地上にプレハブの事務所を設け、自動車の展示場を営んでいました。
この土地は、借地権の決定された土地に該当し、土地の評価額を算定する際、借地権割合分の減額を受けることはできるのでしょうか?
これらの疑問に正確に答えるには、民法の規定や判例を把握している必要があります。
こうした知識も把握していなければ、適切な相続税の申告を行うことはできません。
4 相続税を依頼する場合の税理士の選び方
相続税については、スポットで受任する税理士が多く、普段から相続税の案件を担当している税理士は少数派でしょう。
少数派である相続税に特化した税理士は、普段から相続税の案件を担当し、調査を繰り返していると考えられますので、先に述べたようなポイントを押さえている可能性が高いといえます。
相続税を依頼する税理士を選ぶ際には、相続税に特化しているかどうかを1つの判断材料とすることをおすすめします。
NISAと相続税
1 株式、投資信託への課税

前提として、株式、投資信託については、配当、分配金、売却益について課税がなされています。
株式を保有していると、定まった時期に配当が発生することがあります。
投資信託も、商品によっては、定まった時期に分配金が発生することがあります。
これらの配当、分配金については、所得税、住民税が課税されます。
特定口座で源泉徴収ありの場合ですと、所得税、住民税として20.315%の源泉徴収がなされます。
株式、投資信託を購入したあと、これらが値上がりした場合には、売却により売却益が生じることとなります。
この売却益についても、同様に所得税、住民税が課税されることとなります。
特定口座で源泉徴収ありでしたら、同じく20.315%の源泉徴収がなされます。
2 NISAとは
NISA(少額投資信託非課税制度)は、一定の株式、投資信託の配当、分配金、売却益について、非課税とされる制度です。
NISA口座を設け、NISA口座で株式、投資信託の取引を行うと、配当、分配金、売却益が非課税となります。
ただし、非課税となるのは毎年120万円までであり、非課税期間は最長5年です。
3 NISAと相続
被相続人のNISA口座の株式、投資信託が相続された場合には、相続人の口座へ移管されることとなります。
このとき、移管先となる相続人の口座は、必ず課税口座になります。
仮に相続人がNISA口座を持っていたとしても、そのまま相続人のNISA口座へ移管することはできません。
このとき、被相続人のNISA口座の株式、投資信託については、被相続人が亡くなった時点で、一旦、亡くなった時点の評価額で払い出しがされたものと扱われます。
そして、亡くなった時点の評価額で含み益が生じていたのでしたら、その含み益については非課税となります。
他方、相続人は、亡くなった時点の評価額を取得価額として株式、投資信託を取得したものと扱われます。
このため、亡くなった時点の評価額からさらに値上がりした場合には、亡くなった時点からの値上がり分に限って、所得税、住民税が課税されることとなります。
4 相続税の課税
NISAで非課税となるのは、所得税、住民税です。
そのため、NISA口座の株式、投資信託を相続した場合には、通常の株式、投資信託と同様、相続税が課税されることとなります。
株式については、通常どおり、以下の金額のうち、最も低い金額が評価額とされます。
・ 亡くなった日の終値
・ 亡くなった月の終値の平均
・ 亡くなった月の前月の終値の平均
・ 亡くなった月の前々月の終値の平均
投資信託については、以下の評価方法を用いることとなります。
亡くなった日の1口あたりの基準価額×口数-信託財産留保額・解約手数料
通常の投資信託ですと、亡くなった日に解約した場合の源泉所得税・住民税も差し引いて評価することができますが、NISA口座の場合は、所得税・住民税が非課税となりますので、これらを差し引いて評価することはできません。
税理士による相続税の申告のための不動産の調査
1 相続税の申告のための不動産の調査

相続税の課税対象になる財産の中で、大きな比重を占めているのが、不動産です。
以下では、不動産を調査する際のポイントをまとめていますので、参考にしていただければと思います。
2 不動産の一覧を網羅的に把握する
相続税の申告書を作成する前提として、被相続人が所有していた不動産の一覧を網羅的に把握する必要があります。
そもそも、被相続人が所有していた不動産について、おおまかな情報しかないことも、しばしばあります。
このような場合には、どうすれば、被相続人が所有していた不動産を網羅的に調べることができるのでしょうか。
1つの方法として、毎年4月から5月に届く固定資産税納税通知書の記載を確認することが考えられます。
固定資産税納税通知書には、被相続人が特定の市町村で所有している不動産の一覧が記載されています。
固定資産税納税通知書を紛失した場合には、市町村役場において、名寄帳(固定資産課税台帳)を取得することが考えられます。
名寄帳(固定資産課税台帳)には、公衆用道路やため池等、固定資産税が非課税になっている不動産も記載されていますので、より網羅的に、不動産の一覧を把握することができます。
3 土地の現在の状態を把握する
不動産を評価するにあたっては、机上で書類を確認するだけでなく、実際に現地へ行き、不動産の土地の現状を把握しなければならないことがあります。
例えば、固定資産税納税通知書や名寄帳(固定資産課税台帳)では農地と記載されている土地であっても、現地へ行って現在の状態を確認すると、灌木が生い茂り、到底、農地として利用できないことが判明する場合があります。
もちろん、事実上農地として使用していないだけの場合は、農地として評価されることとなりますが、農地の状態を回復するのに著しい費用を要する場合は、原野や山林として評価し得ることがあります。
原野や山林としての評価額は、農地としての評価額よりも低額になる可能性があります。
税理士による相続税の申告のための金融資産の調査
1 相続税の申告のための金融資産の調査

相続税の申告を行う前提として、被相続人が所有していた相続財産を調査する必要があります。
相続財産の調査に漏れがあると、申告書において、相続財産の記載漏れが生じてしまいます。
後日、税務調査の結果、申告書に記載のない相続財産の存在が判明すると、追加で納税しなければならないだけでなく、加算税や延滞税を納付しなければならなくなります。
税務署が、故意に申告書に記載しなかったと判断した場合には、加算税の税率も重くなるおそれがあります。
このことから、相続税の申告では、どれだけ財産の調査を網羅的に行うことができるかが勝負になるといえます。
以下では、金融資産を網羅的に調査する方法について、具体的に、いくつかのポイントを説明したいと思います。
2 通帳の記載に注意する
通帳の記載からは、様々な情報を得ることができます。
通帳の断片的な記載から、どれだけ相続財産についての情報を得ることができるかは、重要なポイントになります。
通帳に特定の会社からの振込が定期的にある場合には、その会社の株式や社債が存在する可能性があります。
上場していない会社や、古くから株式や社債を保有している会社については、直接、被相続人の口座に配当金や利子が入金されている可能性があります。
これらについては、証券会社の残高報告書では把握することができないでしょうから、通帳の記載を見逃さないようにしなければなりません。
また、被相続人の口座から多額の送金がなされている場合は、送金相手に対する贈与が存在する可能性があります。
相続人や生命保険金の受取人に対して贈与された金融資産は、相続税の課税対象になる可能性がありますので、しっかり把握しておく必要があります。
このように、通帳の記載からは、様々な情報を読み取ることができ、被相続人の金融資産の所在についての手がかりを得ることができます。
もし、通帳が残っていないのでしたら、銀行で出入金履歴を取り寄せて調査を行うことも必要不可欠になってくるでしょう。
3 名義預金に注意する
相続税の申告において、最も申告漏れが起きやすいといわれているのが、名義預金です。
被相続人以外の人の名義になっている預貯金であっても、被相続人が貯めた預貯金であり、生前、被相続人が通帳や証書、銀行印の管理を行い、名義人が出金することもなかったものについては、名義預金と扱われ、実質的には被相続人の財産であるとされる可能性があります。
こうした預貯金については、名義が被相続人以外の人になっているという理由だけで相続税の申告書に記載しなかった場合、後日、税務調査の際に相続財産に該当するとの指摘を受け、加算税や延滞税が課税されるおそれがあります。
さらに、名義預金については、意図的に申告対象にしなかったとして、重加算税の課税がなされるおそれが大きいといわれています。
このような事態を避けるためには、名義預金の存在に注意する必要があります。
例えば、被相続人の自宅を確認したところ、日記帳やメモ書きが見つかり、それらに、被相続人の以外の人の預貯金の口座番号や金額が記載されていることがあります。
実際に銀行に問い合わせて、該当する預貯金が存在することが判明したのでしたら、基本的には名義預金として相続税の申告対象にしなければならないでしょう。
被相続人が給与所得者の場合の相続税についての注意点
1 被相続人が給与所得者の場合は課税対象に注意

相続税は、すでに退職され、年金で生活されている方が亡くなられた際に課税される場合だけでなく、給与所得者が亡くなられたことで課税される場合もしばしばあります。
給与所得者が被相続人となる場合は、相続税の課税対象となる財産で、いくつか注意しなければならないものがあります。
以下でその具体例を挙げたいと思います。
2 未支給の給料
給与所得者が亡くなった時点で、未支給の給料がある場合がしばしばあります。
亡くなった後に会社や雇用主から支払われた給与があれば、相続時点では給与の支払いを受ける権利があったこととなりますので、未支給の給与として、相続税の課税対象となります。
未支給の給与については、相続税申告の際、相続財産として挙げることを見逃しがちですので、注意する必要があります。
3 死亡退職金
給与所得者は、退職時に退職金を受け取ることがあります。
給与所得者が亡くなった場合には、本来退職時に受け取ることができたはずの退職金を、死亡を理由として支給されることがあります。
このように、死亡を理由として支給される退職金のことを、死亡退職金といいます。
死亡退職金は、みなし相続財産となりますので、相続税の課税対象となることに注意が必要です。
もっとも、死亡退職金については、生命保険金と同様、「500万円×法定相続人数」の非課税限度額が存在し、非課税限度額を超える部分に限り、相続税が課税されることとなります。
なお、死亡退職金は、会社から支給されることが多いですが、会社が運用委託している信託銀行等から支給されることもあります。
信託銀行等からまとまった入金があった場合は、死亡退職金に該当するかどうかをきちんと区別する必要があります。
4 会社や雇用主から支払われる弔慰金、花輪代、葬祭料
給与所得者が亡くなった場合には、会社や雇用主から弔慰金、花輪代、葬祭料といった金銭が支払われることがあります。
これらについても、一定の金額を超える部分については、死亡退職金とみなされ、相続税の課税対象となります。
一定の金額とは、以下のとおりです。
- ・ 業務上の死亡の場合→3年分の普通給与
- ・ 業務上の死亡でない場合→半年分の普通給与
一定の金額を超える部分については、死亡退職金とみなされますので、さらに「500万円×法定相続人数」を超える金額に限り、相続税の課税対象になります。
5 相続税の課税対象とならないもの
亡くなったのが国家公務員、地方公務員、学校の先生である場合は、共済組合から弔慰金、埋葬料が支払われることがあります。
具体的には、以下のとおりです。
- ・ 国家公務員共済組合法に規定する弔慰金、埋葬料
- ・ 地方公務員等共済組合法に規定する弔慰金、埋葬料
- ・ 私立学校教職員共済法に規定する弔慰金、埋葬料
これらについては、相続税の課税対象ではないものとされています。
このように、個々の状況によって課税対象となる場合とならない場合があります。
どれが相続税の課税対象となるのか詳しく知っているという方は少ないかと思いますので、適切な相続税申告を行うためにも、一度税理士にご相談いただくことをおすすめします。
相続放棄と相続税
1 法定相続情報証明制度について
相続放棄を行ったとしても、相続税を納付しなければならない場合があります。
それは、相続放棄を行った人が死亡保険金の受取人に指定されており、多額の死亡保険金を受け取ることとなった場合です。
死亡保険金は、遺産ではなく受取人の財産であるとされているため、相続放棄を行っても受け取ることはできますが、みなし相続財産として相続税が課税される対象となります。
例として、以下のような例を考えてみます。
・ 相続人が実子1人
・ 相続財産が1000万円
・ 相続債務が2000万円
・ 死亡保険金が8000万円、受取人は実子
このような例では、相続債務が相続財産を上回っているため、相続人の対応としては相続放棄を行うことが考えられます。
そして、相続放棄を行ったとしても、死亡保険金の受取人に指定されているため、実子は死亡保険金を受け取ることができます。
2 相続税課税価格の計算例
上記の例で、相続税の課税価格を計算すると、以下のとおりとなります。
・1000万円【相続財産】+8000万円【死亡保険金】-2000万円【相続債務】=7000万円【純資産価額】
・7000万円【純資産価額】-3600万円【相続税の基礎控除額】=3400万円【相続税の課税対象となる総額】
このように、死亡保険金が純資産価額に加算されることで純資産価額が基礎控除額を上回る場合には、相続税が課税されることとなり、申告と納付が必要となります。
上記の例ですと、課税対象が3400万円のため、およそ480万円の相続税が課税されることとなります。
相続放棄したのだから相続税の申告はしなくてよいと思われる方も多いかと思いますが、このようなケースもあるため注意が必要です。